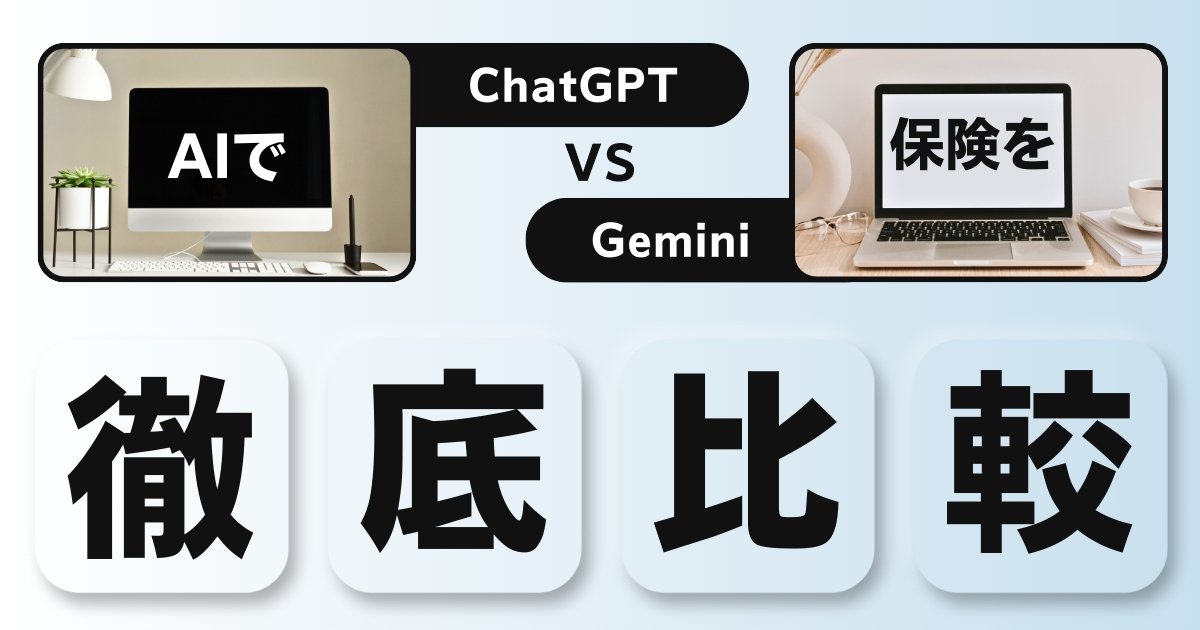こんにちは!「AIライフ探求部(タンキュー部)」部長のアキです。
このブログは、「AIで、時間に余白を。人生に遊び心を。」をテーマに、40代からの人生の後半戦をAIという最高の相棒と人生を豊かにする方法を探求していく、大人のための部活動をテーマにしたブログです。
このブログで得られること:
この部活動では、例えばこんな未来を目指しています。
- 趣味や日々の暮らしを、AIでもっと面白くするアイデア
- 仕事や雑務をAIで効率化し、自分の時間を増やすヒント
- AIを活用して、心と体を賢く、楽に管理する方法
- AIを相談相手に、お金の不安を解消し、賢く備える知識
どうぞ、ゆるやかにお付き合いください。
突然ですが、「保険」という言葉に、少し身構えてしまうことはないでしょうか。
大切だと理解しつつも、複雑で何が最適なのか分かりにくく、つい後回しにしてしまいがちですよね。
何を隠そう、僕自身もその一人でした。そんな面倒な保険選びを「AIに任せられたら…」という考えから、ある実験を思い立ったのです。
それは、Googleの「Gemini」とOpenAIの「ChatGPT」という2大AIに、全く同じ家庭状況を伝えて「おすすめの保険プラン」を提案してもらう、というもの。
すると、返ってきた答えが驚くほど異なり、非常に興味深い結果が得られました。
どちらが優れているという単純な話ではなく、AIにも「得意な役割」があると明確に理解できたのです。
この記事は、僕の実験から見えてきた「AIを保険選びのパートナーにするための具体的な方法」をまとめた活動レポートです。
この記事でわかること
- GeminiとChatGPTの「性格」や「得意分野」の違い
- AIに保険相談をするときの「注意点」と「賢い使い方」
- コピペで使える、AIへの「魔法の質問テンプレート」
- 複雑な保険選びの「思考を整理する具体的なステップ」
保険に苦手意識がある方でも、きっと「なるほど、これなら自分にもできそうだ」と感じていただけるはず。
それでは早速、本日の探求活動を始めましょう。
【はじめに、大切なお願い】
この記事は、あくまで一個人の実験結果を共有するものであり、特定の保険商品や会社を推奨するものでは一切ありません。保険の制度や商品は日々変化します。最終的なご判断は、金融庁などの公的な情報源や、信頼できる専門家にご相談の上でお願いいたします。
AIへの挑戦状:リアルな条件(架空)を提示
今回の実験にあたり、AIには我が家の状況(仮データ)を伝えました。公平な比較のため、両AIには全く同じ情報をインプットしています。
AIに伝えた前提条件
- 家族:私(40代前半・会社員)、配偶者、小学生の子ども2人
- 住まい:賃貸(住宅ローンなし)
- 世帯年収:約600万円
- 金融資産:約500万円
- 現在の保険:未加入(ゼロベースで検討)
さらに、AIへの依頼として「①優先順位と理由を明記」「②情報が不足していれば質問を返す」「③『ミニマム・標準・安心』の3プランで提案」という3点を加えました。
実験の結論:AIは万能な先生ではなく「役割の違う、優秀な相談役」
そして導き出された回答は、実に示唆に富むものでした。結論からいうと、下記のようなイメージです。
- ChatGPTは、まず「国の公的制度でどれだけカバーされるか」を説明し、不足分を補う形を提案する『丁寧なプランニングコーチ』のような存在でした。
- Geminiは、最初に「ご要望の3プランはこちらです」と選択肢を提示し、全体像の把握を促す『仕事が早いデータアナリスト』といった印象です。
どちらも非常に優秀ですが、得意なアプローチが異なります。この「性格」を理解して使い分けることが、AI活用の鍵となりそうです。
【アキ部長メモ】GeminiとChatGPT、提案スタイルの比較
僕が感じた「性格の違い」を比較表に整理しました。
どちらのタイプがご自身のスタイルに合いそうか、ぜひご覧ください。
| 比較ポイント | ChatGPT (丁寧なプランニングコーチ) | Gemini (仕事が早いデータアナリスト) |
|---|---|---|
| 初期アプローチ | 前提知識(公的制度)の確認から始め、対話を通じて深掘りする。 | まず結論(3つの案)を提示し、そこから詳細を調整していく。 |
| 強み | 「なぜこれが必要か」という論理的背景が理解しやすく、応用が利く。 | 選択肢を素早く比較検討でき、全体像とゴールを早期に把握できる。 |
| 留意点 | 丁寧な分、回答が長くなる傾向がある。 | こちらの前提条件が曖昧だと、提案の精度が落ちる可能性がある。 |
| おすすめの活用シーン | 物事の仕組みからじっくり理解したい時に。 | まずは選択肢と相場感を素早く知りたい時に。 |
AIが示した「3つのプランの考え方」が本質的だった
AIは具体的な商品名や保険料を提示しません。それは個人の状況によって大きく変動するため、当然のことです。
しかし、AIが示した「プランニングの考え方」は、非常に本質的で参考になるものでした。
ミニマムプラン
目的:万が一の際、家族の生活基盤が崩れないための最低限の備え。
思考法:公的保障や貯蓄で不足する部分のみを保険で補填。特に家計の主たる収入源を守ることを最優先とします。
標準プラン
目的:生活基盤に加え、子どもの教育など将来の選択肢を守ること。
思考法:ミニマムプランに加え、病気やケガによる収入減少リスクも考慮に入れます。
安心プラン
目的:発生確率は低いものの、家計への影響が甚大なリスクにも備えること。
思考法:長期的な就業不能や介護なども視野に入れます。ただし保険料とのバランスを慎重に検討する必要があります。
全ての基本となる「公的保障」という土台
ここが本日の探求活動で最も重要なポイントかもしれません。
私たちが漠然と不安に思う医療費ですが、日本には非常に手厚い「公的医療保険」というセーフティネットが存在します。
病院窓口での自己負担は原則3割ですし、ひと月の医療費が高額になっても「高額療養費制度」により、自己負担額には上限が設けられています。
つまり、「医療費で自己破産」という事態は、基本的には起こりにくい社会制度になっているわけですね。(もちろん、差額ベッド代など対象外の費用もあります)
 アキ部長
アキ部長民間の保険を検討する大原則は、この「公的保障」という土台でカバーしきれない部分を、ピンポイントで補うという考え方です。この視点を持つだけで、過剰な保険料負担を避けることができます。
【実践編】AIを最強の思考整理パートナーにする手順とテンプレート
今回の実験から導き出した結論は、「AIに答えを求めるのではなく、自分の思考を整理するパートナーとして活用するのが最も賢い」ということです。
そのために僕が色々試した中で手応えを感じた、AIを使いこなすための具体的な手順と、コピー&ペーストで使える質問テンプレートをあなたにご紹介します。
- STEP1 自分の状況と価値観を伝える家族構成といった基本情報に加え、「月々の保険料は〇円まで」「子どもの教育資金を最優先したい」など、ご自身の価値観を正直に伝えます。
- STEP2 まず「公的保障」の説明を求める「私の状況で利用できる公的制度を教えてください」と、全ての土台となる情報の確認から入ることが重要です。
- STEP3 「不足分」に対する3案を依頼する「その上で不足するリスクに対し、ミニマム/標準/安心の3案を理由と共に提案してください」と依頼します。これにより、客観的な選択肢が得られます。
そのまま使える質問テンプレート
あなたは優秀なライフプランアドバイザーです。日本在住の私に、家族の保障に関する客観的な情報提供と、思考の整理を手伝ってください。 # 私の状況 * 【家族】大人2人、小学生2人 * 【収入】世帯年収 約600万円 * 【金融資産】約500万円 * 【住まい】賃貸(住宅ローンなし) * 【希望・価値観】毎月の保険料は【1万5千円】以内が理想です。最も守りたいものは【子どもの教育資金】です。 # 依頼事項 1. まず、私の状況で利用できる「公的保険制度(社会保障)」について、専門用語を避けて分かりやすく説明してください。 2. 次に、公的制度だけでは不足する可能性があるリスクを、優先順位をつけて箇条書きで挙げてください。 3. 最後に、その不足分を補うための考え方を「ミニマム」「標準」「安心」の3つのプランに分け、それぞれの目的・メリット・注意点を添えて提案してください。
このテンプレートをコピーし、【】の中身をご自身の状況に書き換えるだけで、AIから質の高い回答を引き出すことができます。ぜひ、お試しください。
僕自身も陥りかけた「保険選びの落とし穴」と、その回避策
AIとの対話を通じて、僕自身も思わず陥りそうになった「思考のワナ」がいくつか見えてきました。皆さんの参考になれば幸いです。
- 落とし穴①:「人気ランキング1位」を信じ込む
→ 回避策:他者の最適が、自分の最適とは限りません。まずは「自分や家族が、何を最も守りたいか」を明確にすることから始めましょう。 - 落とし穴②:「念のため」で特約を付けすぎる
→ 回避策:「なぜこの保障が必要なのか」を具体的に説明できないオプションは、一度検討から外してみる勇気も必要です。 - 落とし穴③:医療費への不安を過大評価する
→ 回避策:「高額療養費制度」の存在を思い出し、まずは公的保障でどこまでカバーされるかを正しく理解しましょう。 - 落とし穴④:一度契約したら、そのまま放置する
→ 回避策:お子さんの進学、住宅購入など、ライフステージが変化した際は必ず見直しを。年に一度の定期健診をおすすめします。
まとめ:AIは地図を広げるアナリスト、そして共に歩むプランナー
今回の探求活動、いかがでしたでしょうか。
同じ問いを投げかけても、Geminiは客観的な地図を素早く広げて全体像を示し、ChatGPTは丁寧な対話で共に歩む道筋を照らしてくれました。
これらはまさに、役割の異なる、2人の優秀なパートナーだと言えるでしょう。
複雑で敬遠しがちな保険選びも、このようにAIを「思考の壁打ち相手」として活用すれば、まるで自分だけの戦略を練るような、前向きな活動に変えることができます。
専門家に相談する前に、まずはAIをパートナーにご自身の考えを整理してみる。
それが、私たち現代人にとっての、賢い第一歩なのかもしれません。
今日の探求活動が、少しでもお役に立てたら嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ご参考:一次情報の確認も大切な探求活動です
今回の記事執筆にあたり、私が参考にした公的な情報源です。ご自身で一次情報に触れてみることも、非常に重要な探求活動となります。
- 金融庁|公的保険と民間保険の基礎
https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html - 厚生労働省|高額療養費制度(医療費の自己負担に上限がある制度)
https://www.mhlw.go.jp/…/kougakuiryou/ - 金融庁|保険の選び方のポイント資料
https://www.fsa.go.jp/teach/kou4.pdf - 消費者庁|「保険金で実質無料修理」等の勧誘に関する注意喚起
PDF(2024/06/27) - 国民生活センター|保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_2.html
【免責事項】
この記事に掲載されている情報は、執筆時点(2025年8月19日)のものです。AIの回答精度や各種制度は変更される可能性があります。当ブログの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。金融商品の最終的なご判断は、ご自身の責任においてお願いいたします。