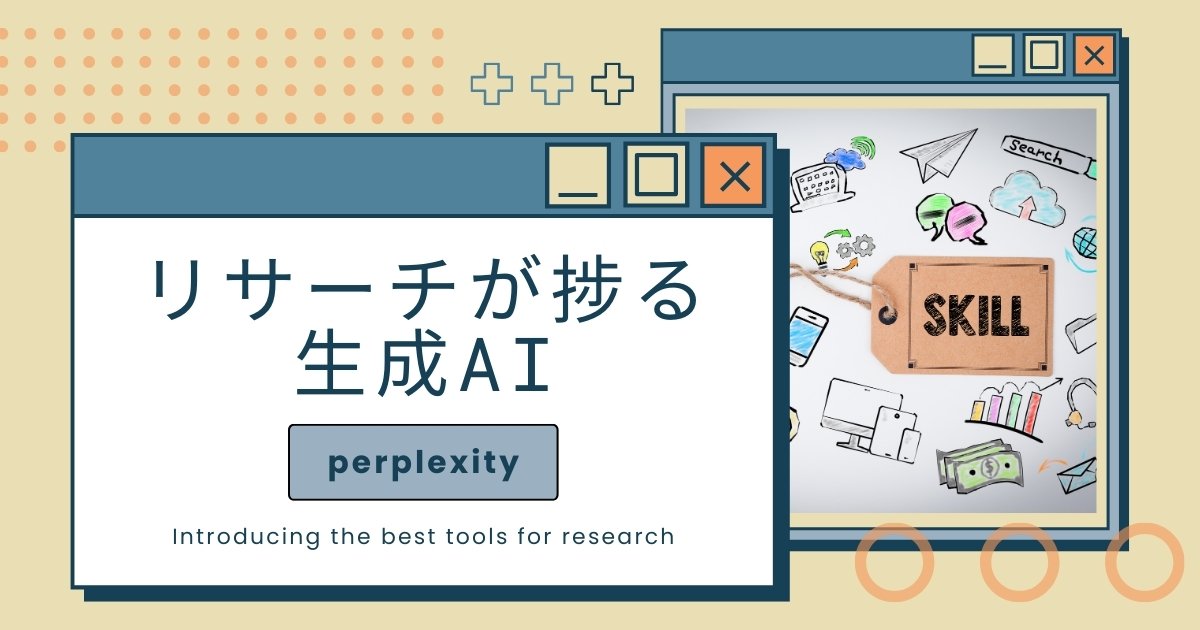こんにちは!「AIライフ探求部(タンキュー部)」部長のアキです。
このブログは、「AIで、時間に余白を。人生に遊び心を。」をテーマに、40代からの人生の後半戦をAIという最高の相棒と人生を豊かにする方法を探求していく、大人のための部活動をテーマにしたブログです。
このブログで得られること:
この部活動では、例えばこんな未来を目指しています。
- 趣味や日々の暮らしを、AIでもっと面白くするアイデア
- 仕事や雑務をAIで効率化し、自分の時間を増やすヒント
- AIを活用して、心と体を賢く、楽に管理する方法
- AIを相談相手に、お金の不安を解消し、賢く備える知識
どうぞ、ゆるやかにお付き合いください。
さて、今回の活動報告は、ブログを書く僕たちにとって、永遠の課題とも言える「リサーチ(情報収集)」がテーマです。
「この記事、本当に正しい情報かな…?」「いろんなサイトに違うことが書いてあるけど、どれを信じれば…?」
信頼できる情報源を探して、いくつものWebサイトを渡り歩き、気づけば1時間…なんてこと、日常茶飯事ですよね。僕も、ネットの海で遭難しかけては、「もう、書くのやめようかな…」と心が折れかけたことが何度もあります。
そんな僕の“リサーチ地獄”を、一瞬で天国に変えてくれた、まさに「神ツール」と呼ぶべきAIに出会ってしまいました。それが、対話型検索エンジン「Perplexity AI」です。
今回は、このPerplexity AIが、なぜ僕たちブロガーやビジネスパーソンにとって心強いの相棒となり得るのか、その感動的な実力を、余すところなくお伝えします。
この記事を読めば…
- Perplexity AIとは何か?ChatGPTとの決定的な違いがわかる
- 情報収集の時間が1/10になる、具体的な使い方がわかる
- ブログ記事の「信頼性」と「質」を劇的に向上させる方法がわかる
- リサーチのストレスから解放され、書くことがもっと楽しくなる
Perplexity AIとは?一言でいうと「超優秀な、司書さん」です
「また新しいAI?ChatGPTと何が違うの?」と思いますよね。僕も最初はそうでした。
一言で違いを説明するなら、こうです。
- ChatGPT:物知りだけど、どこでその知識を仕入れたか教えてくれない、雑学王の友達
- Perplexity AI:質問に答えてくれるだけでなく、「その答えは、この本のこのページに書いてありますよ」と、情報源(ソース)まで示してくれる、超優秀な図書館の司書さん
そう、Perplexity AIの最大の特徴は、AIが回答を生成するために参考にしたWebサイトのリンクを、必ず一緒に提示してくれること。
これにより、情報の「裏取り(ファクトチェック)」が驚くほど簡単になるんです。
なぜ、Perplexity AIがブログリサーチで“神”なのか?3つの理由
① 出典元がわかる、圧倒的な「信頼感」
ブログ記事で最も大切なことの一つは、情報の正確性です。Perplexity AIは、回答の文章中に[1] [2]といった形で番号を振り、どの部分がどのサイトを参考にしているかを明記してくれます。
これにより、「AIが言っているから」というフワッとした情報ではなく、「公的機関のサイトにこう書かれているから」という、根拠に基づいた質の高い記事を、自信を持って書くことができます。
② 複数サイトを渡り歩く手間がなくなる「究極の時短」
これまで僕たちは、Googleで検索しては、1位、2位、3位…と複数のサイトを開き、それぞれの情報を比較検討していましたよね。Perplexity AIは、この作業をすべて自動でやってくれます。
一つの質問を投げかけるだけで、複数の信頼できる情報源から要点を抜き出し、一つの文章にまとめてくれる。これまで1時間かかっていたリサーチが、ものの5分で終わる。
これはもはや革命です。
③ 関連質問の提案で、記事がどんどん深掘りできる「知的好奇心の相棒」
Perplexity AIのすごいところは、ただ答えて終わり、ではないことです。回答の下には、必ず「関連する質問」をいくつか提案してくれます。
例えば、「新NISAとは?」と聞くと、「新NISAのデメリットは?」「iDeCoとの違いは?」といった、読者が次に知りたくなるであろう質問を先回りして提示してくれるんです。
これをクリックしていくだけで、自然と記事の構成が出来上がっていきます。まさに、知的好奇心を刺激してくれる最高の相棒です。
【実録】アキ部長がPerplexity AIで「新NISA」の記事ネタをリサーチしてみた
では、実際に僕が「新NISA」について調べてみた過程をご覧ください。その便利さに、きっと驚くはずです。
Perplexityのサイトに行き、「新NISAとは?初心者にも分かるように教えて」と入力しました。
数秒後、新NISAの概要が、出典元のリンク[1][2]…と共に、非常に分かりやすく要約されて表示されました。この時点で、もう複数のサイトを開く必要がありません。
回答の下に表示された「新NISAのメリットとデメリットは?」という関連質問をクリック。すると、今度はその答えが、新たな出典元と共に表示されます。これを繰り返すだけで、記事に必要な情報がどんどん集まっていくんです。
 アキ部長
アキ部長実際にperplexityにリサーチをしてもらった結果を下記に記載しますね
新NISAの要点
新NISAは2024年1月1日から始まった、投資による利益が非課税になる「NISA(少額投資非課税制度)」の改正版です。これまで別々だった「つみたてNISA」と「一般NISA」が一本化され、より大きな非課税投資枠と無期限の非課税保有期間が特徴です。
1. 新NISAの主な特徴
新NISAでは以下の4つが大きく変わりました。
- 制度の恒久化
従来は期間限定だった口座開設期間が無期限化され、いつでも新規開設が可能です。 - 無期限の非課税保有期間
これまで「つみたてNISA」は20年、「一般NISA」は5年だった非課税期間が、どちらも無期限になりました。 - 年間投資上限額の大幅拡大
- 生涯非課税限度額の設定
一人あたり合計1,800万円(成長投資枠1,200万円、つみたて投資枠600万円)の非課税保有限度額を、新たに買付残高(簿価)方式で管理します。売却した分は翌年以降に再利用可能です。
2. つみたて投資枠 vs. 成長投資枠
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(内、成長枠1,200万円) | 同左 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 対象商品 | 金融庁が指定した長期・分散投資向け投資信託のみ | 株式(国内外)、ETF、REIT、投資信託など幅広い商品 |
| 買付方法 | 積立のみ | 一括・積立可 |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
- つみたて投資枠は、長期・分散投資向けの投資信託に限定され、初心者でもコツコツ続けやすい。
- 成長投資枠は、よりリスクを取ってリターンを狙う株式やETFなども選択できる。
3. 新NISAのメリット・デメリット
メリット
- 税制優遇効果の強化:年間360万円、かつ生涯1,800万円まで非課税で運用可能。
- 長期投資に最適:非課税保有期間が無期限のため、長期的な資産形成に向く。
- 併用自由:つみたて投資枠と成長投資枠を同一年に併用でき、投資戦略の幅が広がる。
- 売却後の枠再利用:売却した分の非課税枠を翌年以降に再利用できる。
デメリット・注意点
- 投資対象の選定が必要:成長投資枠では株式など選択肢が増える分、銘柄選びが重要。
- 上限管理:年間・生涯の投資上限を超えないよう注意が必要。
- 金融機関の選択:手数料や取り扱い商品は証券会社によって異なるため、事前に比較検討が必要。
4. 新NISAの始め方(簡単ステップ)
- 金融機関の口座開設
証券会社や銀行で「NISA口座」を開設。2023年末までに旧制度口座を持っていた場合は自動移行される場合もある。 - 投資枠の選択
つみたて投資枠、成長投資枠、または両方の利用枠を決定。 - 商品選定
自分のリスク許容度や投資目標に合わせ、投資信託や株式等を選ぶ。 - 積立・買付設定
定期積立の金額設定や、スポット買付を行う。 - 運用状況の確認・調整
定期的にパフォーマンスをチェックし、必要に応じてポートフォリオをリバランス。
新NISAは、初心者でも長期の資産形成を手厚い税制優遇のもとで始めやすい仕組みです。制度改正を活かして、自分に合った投資スタイルで次の一歩を踏み出しましょう。
この体験は、まさに「目からウロコ」でした。リサーチって、こんなに楽しくて、クリエイティブな作業だったんだな、と。
まとめ|リサーチはAIに任せて、僕たちは「書くこと」に集中しよう
僕たちブロガーやコンテンツを作る人間の仕事は、「情報を探す」ことではなく、「集めた情報を、自分の体験や言葉で、読者に分かりやすく届ける」ことのはずです。
Perplexity AIは、その一番面倒で時間のかかる「信頼できる情報を探す」という作業を、完璧に肩代わりしてくれます。
AIで生まれたその膨大な「時間の余白」を、僕たちはもっと記事の構成を練ったり、読者の心に響く言葉を考えたり、という、人間にしかできない創造的な作業に使うことができるようになります。
情報の洪水に溺れそうなあなたも、ぜひ「Perplexity AI」という名の超優秀な司書さんを、今日からあなたのチームに加えてみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました!